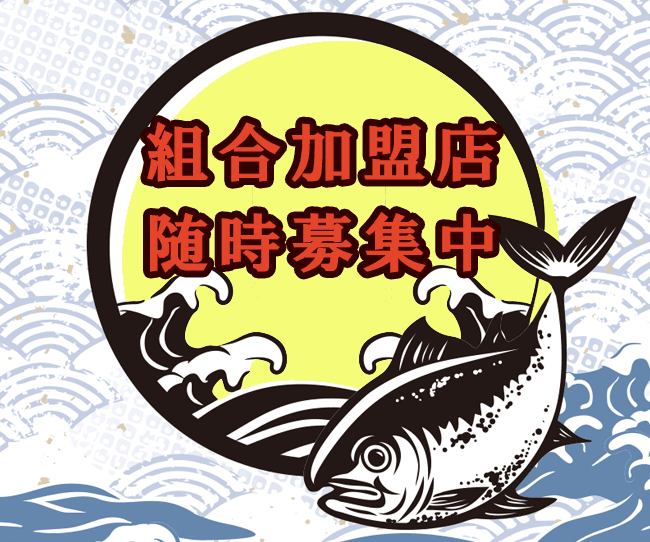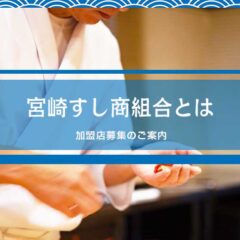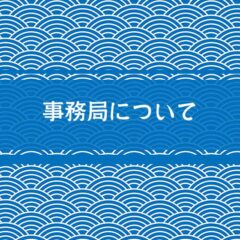すしのあれこれ

日本食文化の代表格として「すし」は今や世界のいたるところで食されるまでになった。近年、和食が体にやさしい食べ物であることから、アメリカはもとよりヨーロッパやオーストラリアと大陸への進出も目覚ましい。いわんや外国から日本のすしとは少々違う形や味のすしが逆輸入され日本のすし店で販売される商品も登場しているありさまである。すでに日本だけのすし食文化ではなく、世界の食の一部でもある感じがする。
米食文化がいかに体に良いかが最近クローズアップされ米を使った「すし」の良さが再認識されたのは確かだ。
日本の「すし」は古来より、全国各地でその地方の郷土ずしとして形を変え、進化してきた。近江の「鮒ずし」、これがすしの起源として分化していった。いわゆる「馴れずし」である。安土・桃山時代のころから現代のすしの基本が形成され、明治、大正、昭和と急速に発展し、近代のすしへとなったのであろう。
すしには、長い歴史とともに培われてきた多様な文化と技があります。
関西では、箱ずしや巻きずしなど、日持ちや美しさを重んじたすしが受け継がれ、関東では、江戸前の新鮮な魚介を生で味わう粋な食文化として発展してきました。
時代が移り変わる中で、すし職人の技や心は、常に新しい挑戦とともに進化しています。
「伝統を大切にしながら、未来へつなぐ」――それこそが、私たちが守り続けたい“すしの姿”です。
歴史を振り返れば、行商や屋台から始まったすしは、常設店舗、そして回転ずしなど、時代の変遷とともに多様な形態へと発展してまいりました。
今日では、デパートやスーパー、コンビニなどでも気軽にすしを楽しめるようになり、すしは日本を代表する大衆食として国民の食卓に広く浸透しております。
伝統を守りつつも新たな形に挑戦する。これもすし文化の魅力であり、今後も進化を続けていくことでしょう。
現代では、インバウンド効果も有り、すしも大量消費の時代に入り、より身近な存在となりました。
しかし、職人が一貫ずつ丁寧ににぎる、本来のにぎりずしの味やぬくもりも醍醐味の一つ。
かつて、にぎりずしはお腹を満たすものではなく、軽やかに味わう贅沢とされていました。
その日にぎられたすしを、すぐに口へ運ぶ――そんな一瞬の美味しさを大切にする心も又、日本のすし文化の原点ともいえるでしょう。
ともあれ 、すしは健康にいい、からだにやさしい食であるには違いない。大いに食べるべし、大いに楽しむべし。